動詞の活用は、文法の中でもっとも基本的なことですが、日常会話の中で変容していくことも多々あります。「ら抜き言葉」が良い例です。日常会話で容認されているのでどうしても駄目というわけではないが、文字による何らかの表現手段を用いるなら丁寧におさらいしておいた方がよいでしょう。
無意識な創作と、知識を蓄え意図して作ることでは後々になって大きな差が出てくるからです。
まずは「飛ぶ」という動詞について
文語(古語)と口語(現代語)の活用を見てみましょう。

「飛(語幹)ぶ(活用語尾)」について
| 口語(現代語) | 文語(古語) | |
| 自動詞バ行五段活用 | 自動詞バ行四段活用 | |
| 未然形 | 飛ば・ない/ 飛ぼ・う | 飛ば・ず |
| 連用形 | 飛び・ます | 飛び・たり/ 飛び・し |
| 終止形 | 飛ぶ | 飛ぶ |
| 連体形 | 飛ぶ・とき | 飛ぶ・とき/ 飛ぶ・なり |
| 仮定形 | 飛べ・ば | (已然形)飛べ・ども/ 飛べ・り |
| 命令形 | 飛べ | 飛べ |
五段活用・四段活用とは
(ア・イ・ウ・エ・オ)の段に語尾が変化する活用をいいます。
未然形は打消や否定、推量の助動詞に接続します
古語の四段活用が現代語において五段活用になったのは
未然形に接続する反復・継続の助動詞「ふ」の直前の活用語尾が音変化して「オ」段になったためです。
これを推量形・意志形と呼び、未然形と区別する説もあります。
飛ば・ふ → 飛ば・う → 飛ぼ・う
という訳だ。
ほとんどの場合、口語の五段活用は文語の四段活用になりますが、
そうでない動詞もあります。
以下がその例です。
恨む(五段活用→上二段活用)
在る・有る→在り・有り(五段活用→ラ変活用)
死ぬ(五段活用→ナ変活用)
蹴る(五段活用→下一段活用)ほぼ使わない
阻む(五段活用→下二段活用・四段活用)
また同じ動詞でも、
自動詞としての活用と他動詞としての活用が異なる場合もあるので複雑です。
※動詞には自動詞と他動詞があり、
「~を」という目的語を必要とするものを他動詞、
目的語を必要としない動詞を自動詞と呼び判別します。
活用表を見てみましょう。
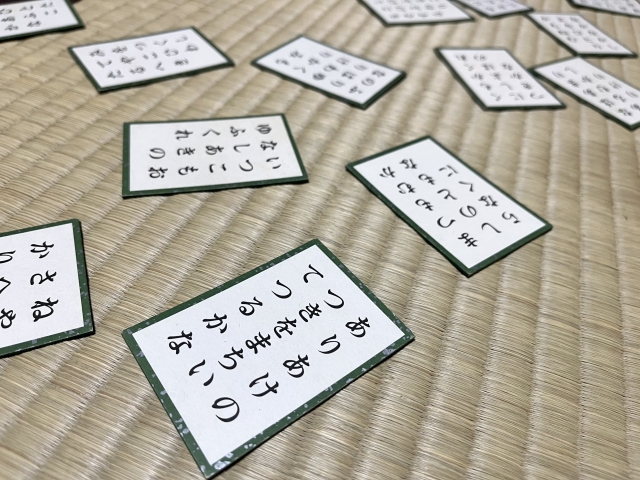
恨む
| 口語(現代語) | 文語(古語) | ||
| 他動詞マ行五段活用 | 他動詞マ行上二段活用 | 他動詞マ行四段活用(近世) | |
| 未然形 | 恨ま・ない | 恨み・ず | 恨ま・ず |
| 連用形 | 恨み・ます | 恨み・たり/恨み・ぬ | 恨み・ぬ |
| 終止形 | 恨む | 恨む | 恨む |
| 連体形 | 恨む・とき | 恨むる・とき | 恨む・とき |
| 仮定形(已然形) | 恨め・ば | 恨むれ・ば | 恨めば/恨めり/恨めども |
| 命令形 | 恨め | 恨みよ | 恨め |
※「恨む」が形容詞になると
「恨めしい」「恨めし」でシク活用。
活用は以下になります。
| 口語(現代語) | 文語(古語) | |
| シク活用 | ||
| 未然形 | 恨めしかろ・う | 恨めしから・ず |
| 連用形 | 恨めしく・思う/ 恨めしかった | 恨めしく・あり/ 恨めしかり・けり |
| 終止形 | 恨めしい | 恨めし |
| 連体形 | 恨めしい・とき | 恨めしき・とき/ 恨めしかる・とき |
| 仮定形 | 恨めしけれ・ば | (已然形)恨めしけれ・ども |
| 命令形 |
在る・有る ⇒在り・有り
| 口語(現代語) | 文語(古語) | |
| 自動詞ラ行五段活用 | 自動詞ラ行変格活用 | |
| 未然形 | あら・ない(とは言わないけれど)/あろう | あら・ず/ あら・む |
| 連用形 | あり・ます | あり・たり/ あり・ぬ |
| 終止形 | ある | あり |
| 連体形 | ある・とき | ある・とき |
| 仮定形 | あれ・ば | (已然形)あれ・ども |
| 命令形 | あれ | あれ |
※状態をあらわす補助動詞として使われることもあります。
※同音異義語
「生る(ある)」……自動詞ラ行下二段活用・神聖なものが生まれるときに使われます。
「荒る(ある」 ……自動詞ラ行下二段活用・荒れる。荒廃する。
「散る(ある)・離る(ある)」………同上 ・遠のく。離れる。
死ぬ
| 口語(現代語) | 文語(古語) | |
| 自動詞ナ行五段活用 | 自動詞ナ行変格活用 | |
| 未然形 | 死な・ない/ 死の・う | 死な・ず/ 死な・む |
| 連用形 | 死に・ます | 死に・たり/ 死に・ぬ |
| 終止形 | 死ぬ | 死ぬ |
| 連体形 | 死ぬ・とき | 死ぬる・とき |
| 仮定形 | 死ね・ば | (已然形)死ぬれ・ども |
| 命令形 | 死ね | 死ね |
※ナ行変格活用動詞は
「死ぬ」「往ぬ(いぬ)・去ぬ(いぬ)」のみである。
「死す」はサ行変格活用動詞となり活用は以下。
| 「死す」自動詞さ行変格活用 | |
| 未然形 | 死せ・ず/ 死せ・り |
| 連用形 | 死し |
| 終止形 | 死す |
| 連体形 | 死する・とき |
| 已然形 | 死すれ・ども |
| 命令形 | 死せよ |
蹴る
| 口語(現代語) | 文語(古語) | |
| 他動詞ラ行五段活用 | 他動詞カ行下一段活用 | |
| 未然形 | 蹴ら・ない/ 蹴ろ・う | 蹴・ず/ 蹴・む |
| 連用形 | 蹴り・ます | 蹴・たり |
| 終止形 | 蹴る | 蹴る |
| 連体形 | 蹴る・とき | 蹴る・とき |
| 仮定形 | 蹴れ・ば | (已然形)蹴れ・ども |
| 命令形 | 蹴れ | 蹴よ |
※文語(古語)における下一段活用は「蹴る」のみ。
語幹と語尾の区別はありません。
口語(現代語)の下一段活用動詞は「得る」「受ける」など多数あり、
多くの場合、文語(古語)においては下二段活用となります。
口語 文語
得る → 得(う)
受ける → 受く
上げる → 上ぐ
出る → 出(い)づ
植える → 植う
※語幹とは
動詞や形容詞、形容動詞において活用変化しない部分のことを言います。
「見る」(miru)における語幹は「見」(mi)
「飛ぶ」(tobu)の場合「飛」(to)、あるいは変化しないなら(tob)を語幹とする説もあります。
※語尾とは
ひと続きの言葉のおわりの部分。
活用によって変化する部分を活用語尾と言います。


