短歌与俳句的区别及其适用性
Differences Between Tanka and Haiku, and Their Strengths
カーテンを閉め切った部屋で辞書を引いたりググったりするよりは魚釣りに行ったり近所の草刈りでもした方がいいと思っています。けれども、ひょんな縁から短歌を始めることとなり、一応日本語についてあれこれ調べるようになりました。
大きな短歌結社の末席に加えさせてもらったこともあり、地方の短歌サークルの歌会に参加したこともあります。
しかし、いつも場違い感がつきまとうのです。
どうもあの「いいですね」で始まる予定調和的空気感に馴染めないのです。こうした空気は、日本の国会を始めとして至る所で感じられることとはいえ、自分は短歌に向いていないのかもしれない……と思いました。
我认为,与其拉上窗帘在房间里查字典或上网搜索,还不如去钓鱼或者帮邻居割草。不过,因为一个偶然的机会,我开始写短歌,于是也多少开始研究起日语的各种知识。
我还有幸加入了一个大型短歌结社的末席,也参加过地方短歌社团的歌会。
但我总是觉得自己格格不入。
我实在无法适应那种以“好棒啊”开头、充满预设和谐气氛的感觉。虽然这种氛围从日本国会到各处都能感受到,但我开始觉得,自己可能并不适合写短歌……
I think it’s better to go fishing or mow the neighbor’s lawn than to sit in a room with the curtains drawn, looking up words in a dictionary or Googling. Still, by some odd twist of fate, I started writing tanka, and I’ve ended up researching various aspects of the Japanese language.
I’ve even been allowed to join the fringes of a major tanka society and have attended local tanka circle gatherings.
But I always feel out of place.
I just can’t get used to that predictable, harmonious atmosphere that starts with “That’s nice, isn’t it?” While I know this kind of vibe is something you encounter everywhere, from Japan’s parliament to all sorts of places, I’ve started to think that maybe tanka isn’t for me…
短歌は貴族のもので俳句は庶民のもの?

「短歌に向き不向きはあるのでしょうか?」と、超有名歌人に尋ねたことがあります。
歌人いわく
「う~ん……短歌は生活の心配をしなくて良い人が多い感じですね。セレブとか、仕事をリタイアした人とか。 俳句だと、会社の社長さんとかが大勢いますね」
ふ~んナルホド
そのどちらでもない自分だから、こんなに喘いでいるのだとおもいました。はなから生きてる土俵が違う……とはいえ、簡単に辞めるわけにはいかない程度の責任を感じつつある昨今です。ダラダラと20年も続けてキャリアの浅い仲間に意見を求められることさえあります。短歌について、最低限のことは押さえておこうと思った次第です。
短歌と俳句の起源とは?
では、短歌と俳句の歴史をみていきます。
人類最初の和歌はスサノオノミコト作
スサノオノミコトといえば、ヤマタノオロチを退治した昔話で有名です。
その須佐之男命(スサノオノミコト)の
「八雲起つ出雲八重垣妻ごみに八重垣作るその八重垣を」
こそが、人類最初の和歌と言われています。
須佐之男命(スサノオノミコト)は八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治したとき、助けた櫛名田比売(クシナダヒメ)をお嫁さんに迎えました。そして、新婚生活を送る新居を探していたところ、島根県出雲地方の須我というところで雲が幾重にも重なる様が自分たちを祝福しているようだと感激し、ここに住もうと思いました。その時に詠んだといわれる人類最古の和歌です。
八雲立つ……出雲に対する枕詞
出雲八重垣……主題である「八重垣作る」を際立たせ調子をとるための言葉
八重垣作る……結婚をすること
八重垣を繰り返すことで八重を強調しています。
俳句は16世紀の「犬筑波集」から
一方の俳句は16世紀の「犬筑波集」 が起源といわれています。犬筑波集とは室町時代後期の俳諧集。滑稽で卑俗な表現を打ち出し俳諧が連歌から独立するきっかけとなった本です。編者は戦国時代の連歌師・諧作者、山崎宗鑑(やまざき そうかん1465~1554年?)
参考文献
ナルホド!天皇は歌を詠むことはあっても俳句はつくらない
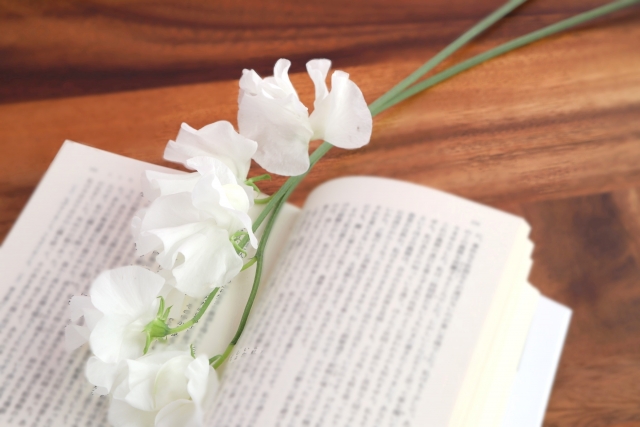
天皇の詠む歌を御製(ぎょせい)と呼び毎年「歌会始」が催されます。けれども天皇の作った俳句作品は聞いたことがありません。
短歌関連本を開くと、短歌は貴族的で俳句は庶民的? という問いへの参考として窪田空穂の長歌「友に寄す」を引用していました。以下、引用になります。
文芸の名に隠れて、貴族趣味にあこがるる人よ。
我は思ふ。
文芸とは貴族の心を持ちて、
平民の道を行ふものなり。
正直に、
率直に、
有りを有りとし、
無きを無きとし、
入用を拾い、
無用を捨て、
平易なる言葉をもて語るべきなりと。(以下略)
※窪田空穂(くぼたうつぼ)1877-1967 明治-昭和時代の歌人,国文学者。
草創期の「明星」に加わり、大正3年「国民文学」を創刊。人生を詠嘆する歌風で人気を博す。 歌集「まひる野」「土を眺めて」「新古今和歌集評釈」などを出版。
貴族の心を持って平民の道を歩いているつもりなのだが、いかんせん忙くて……と、この忙しいという言い訳こそが庶民の証しなのかも知れません。同じような題材を扱った短歌と俳句を紹介します。
春みじかし何に不滅の命ぞとちからある乳を手にさぐらせぬ
与謝野晶子
窓の雪女体にて湯をあふれしむ 桂信子
与謝野 晶子(よさの あきこ)1878~ 1942年。歌人、作家、思想家。
桂 信子(かつら のぶこ)1914~ 2004年。大阪市出身の俳人。
どちらも素晴らしい!だから短歌と俳句、どちらが高尚か庶民的かなんてどうでもよいことです。
短歌と俳句では自ずと表現したいことが異なる?

短歌と俳句の違いが文字数と季語の有無というのは誰もが知っていることです。季語があろうがなかろうがよいのが短歌です。温暖化とか何とかより冷暖房機器と流通の発達で、温度にも旬の食べ物にもすっかり鈍感になってしまった昨今、四季を詠むのが難しくなりました。
和歌は作り手の心情をストレートに述べるものであり、5・7・5・7・7という詩形が、その心地よいリズムゆえか多く作られるようになっていきました。日本人の心から欲するものが自然と形になったもののように思われます。その後歴史を刻むにつれて少しずつ上品に流麗に、心情をズバリと盛り込まず、風景そのものや、作者の目線によって心情を表そうとするようになりました。
そうした流れの中で、詩形そのものを短くし、まるで写真のように一瞬の場面を切り取り、それによって逆に豊かな心情を盛り込もうとしたのが俳句なのではないでしょうか?
したがって、どちらかといえば俳句の方が想像の余地が広いように感じられます。
日本語の持つ七五調の由来とは?
俳句の5・7・5も短歌の5・7・5・7・7も素晴らしく耳に馴染みます。なぜなら、日本語は欧米のようなアクセントによる抑揚がないので字数によってリズムを作るからです。
私たち日本人には、5文字と7文字のリズムが沁みついています。5:7は、西洋の黄金比である5:8(1:1.618~)とは若干異なりますが、これが日本の風土で育まれた黄金比なのかも知れません。
井上ひさしの「2n + 1」説
作家の井上ひさし氏(1934~2010年)は、日本語はリズムになろうとする前に2音ずつの塊となり、助詞を加えて「2n + 1」という公式が成り立つと語っています。たとえば「赤」という塊は「赤々 + と」となり「あかあかと」、こう来たら「燃える暖炉に」とか続くのでしょうか……。この「2n + 1」の公式が成り立つとすれば、七五調は「日本語の宿命」といえるでしょう。
日本語は一音一音に意味がある
日本語が七五調になった理由は他にもあるでしょうが、2音をひと塊とする考え方は、古代文字の一音一音に意味があるという言霊にもつながります。たとえば「御霊」の「み」や「ちはやぶる」の「ち」んどは、霊魂や神といった霊的な意味を持っています。
まとめ
俳句には季節感があり、短文なので想像力を刺激し、何より作りやすい利点があります。
けれどこの気持ちを表現したい、という切なる思いがあって、喜怒哀楽を表現するなら短歌の方が好ましいのかも知れません。短歌の方が俳句より制約が少ないので間口は広いでしょう。
どちらも日本文化を代表する定型詩です。ケースバイケースで作り分けるのも一興。いずれにせよ、少しばかりでも国語の勉強をやっておいた方がよいでしょう……。



