大和言葉是什么?吟诵和询问都充满美丽魅力和意义。
What are Yamato words? Their beautiful charm and meaning, whether recited or inquired about.
日本語には、はるか昔に大陸から入ってきた漢語を中心とした「外来語」と、さらに縄文・弥生時代にまで遡る日本固有の「大和言葉」があります。
漢語を中心とした文字文化が普及する以前の話であり、話し言葉として使われつづけ「音」そのものに意味を持たせていました。
数千年という長い時を超えて、今もなお使われ続けている「大和言葉」の世界を、ほんの少しだけ紹介しよう。
日语中有以古代从大陆传入的汉语为中心的“外来语”,以及可以追溯到绳文和弥生时代的日本固有的“大和言叶”。
这段历史发生在以汉语为中心的文字文化普及之前,作为口语继续使用,使“音”本身具有了意义。
跨越数千年的漫长时光,如今仍在使用的“大和言叶”世界,稍微介绍一下。
In Japanese, there are “loanwords” centered around Chinese characters that entered from the continent long ago, and there are also “Yamato words” that can be traced back to the Jomon and Yayoi periods.
This refers to a time before the spread of a written culture centered on Chinese characters, where spoken language continued to be used, giving meaning to the “sound” itself.
Over the course of thousands of years, I will introduce just a little bit about the world of “Yamato words,” which continue to be used even today.
大和言葉とは?
大和言葉とは、一般的な概念では漢語と外来語を除いた日本の固有語ということになっています。日本の固有語といえば「和語」と同義になりますが、「和語」が漢語・外来語に対する識別を表すのに対し「大和言葉」は大陸文化が伝来する以前の、日本列島で話されていたネイティブな言語そのものを指します。
一方で「和語」としての「大和言葉」も、時代が下ると和歌の万葉ことば「雅語」の意味で使われるようになり、さらに宮中や幕府などの上流階級の婦女子が使う言葉を指すようになりました。
かっこいいだけじゃない大和言葉の深い魅力

大和言葉を知っているとカッコいいとかお洒落とかいわれますが、そうした印象を持たせる深い魅力に満ちていることは確かです。具体的に、以下6つの魅力をご紹介しましょう。
- 健気(けなげ)に多くのニュアンスを含む
- 感性がゆたか
- 身体感覚がありリアル
- 日本文化の香りがするを感じさせる
- 精神が宿っている
- 音から現象をイメージしやすい
それぞれについて解説します。
大和言葉は健気(けなげ)に多くのニュアンスを含む
健気という単語ですらすでに大和言葉であり、説明が必要です。健気とは心掛けがよくしっかりとしたさまを表します。一般的には、弱者とされる人が困難に立ち向かっていたり、気丈に振舞っていたりする場合に用いられます。
たとえば「はな」という2音の言葉で「端」「鼻」「花」を表します。「寝入りばな」や「はなから決まってる」「でばなをくじく」など、いずれも先端、端っこの意味を持ちます。「でばな」は出鼻とも出端とも書き、始めようとしているところを邪魔されるという意味です。顔についている「鼻」も確かに出っ張った先端部分であり、「花」も多くの場合、茎や枝の先端部分に開きます。古代日本人は、「は」と「な」のわずか2音で、健気にもニュアンスの似通った多くのものを表現していたことがわかります。
大和言葉は感性が豊か
たとえば「気」という大和言葉があります。
「空気」の気など、目に見えないものを表すときに使われ、まさに感性の集約された言葉です。
- 気が合う
- 気の置けない
- 気を許す
- 気が付く
- 気を付ける
この「気」に対する日本人の繊細な感性は、人生のさまざまな局面で事態を好転させます。たとえば、サッカーの試合で流れが悪くなったとき監督はタイムを取ったり、授業中に生徒の士気が下がったと感じたら教師は声のトーンを変えたりして気を入れ直すでしょう。
大和言葉には身体感覚が含まれてリアル
大和言葉は体験に基づいた深い意味があります。経験した人にしかわからない、身体感覚が含まれると言い換えてもよいでしょう。
たとえば、「力をふり絞る」というとき、「絞る」という動詞から「雑巾を絞る」ようにこれ以上絞りだせないくらい頑張り通すことが想像できます。雑巾を絞ったことのある人は容易にイメージできるでしょう。
また「計画を練る」という場合の「練る」は、「餡を練る」「味噌を練る」など繰り返しの動作を加えることによって物事を柔らかく粘り強くするときに用いられます。「練る」体験をした方にとって「計画を練る」は、最初の発案をひっくり返したり、考え直したりの根気を伴いながらより良い案にまとめ上げる行為となります。
「計画を練る」と「計画を立てる」とはまったく異なる行為です。「練る」は「考えを練る」「技を練る」など、物事をより深く追求する場合に用いられます。
大和言葉は日本文化の香りがする
その言葉が、どのようなシチュエーションで使われているかよく見まわしてみましょう。日本文化の香りが立ち昇り一段と深く味わうことができます。
たとえば「結ぶ」
- 紐を結ぶ
- 縁を結ぶ
- 契りを結ぶ
- 手を結ぶ
- お結び
- 結びの一番
- 帯結び
それぞれの背景に自ずと日本文化が浮かんできます。
「結ぶ」には、離れているものをつなげることで新しい力を生み出すという意味があります。その一方で、結びつけることは力を封じ込めるとも考えられています。お正月の「しめ縄」が顕著な例です。
「しめ縄」は、神聖な場所と不浄な下界とを区別するために張り巡らされ、新年の「しめ縄」飾りは災いを封じ込めるために飾られます。
大和言葉には精神が宿る
大和言葉には「忌み言葉」というのがあります。「忌み言葉」とは、不吉な言葉や相応しくないネガティブな表現を極力避けてポジティブに言う表現方法です。
たとえば祝宴を終えるとき「お開き」という言葉を使ったり、締めのお茶を「あがり」と言ったりします。つまり「終わる」や「閉じる」というネガティブな表現を避けて「開く」という言葉へ。また、昔のお茶は挽くものであったため、「挽く」という言葉を伴う「お茶」と呼ぶことを避けて「あがり」と呼ぶようになりました。
こうした「忌み言葉」の背景には日本古来の言霊信仰があります。すなわち、言葉には魂・霊力が宿り、よい言葉が良い結果を引き寄せるという考え方です。言葉によって世界を変えられるという考え方は、現代社会を生き抜く大きな指針となるでしょう。
大和言葉は音から現象をイメージしやすい
大和言葉は口に出すことで、その感覚がいっそう高まります。たとえば「楽しい」「嬉しい」と言葉にすると、さらに楽しい・嬉しい気持ちになるでしょう。その理由は、大和言葉の音と、受け取る感覚がつながるからです。
「かたい」は硬い感じがしますし「やわらかい」は音も柔らかく聞こえます。日本語全般として、カ行とタ行は硬い響きを持ち、ヤ行・マ行・ワ行は柔らかい音感です。
大和言葉の音でもっともイメージしやすいのは、オノマトペと呼ばれる擬音語・擬態語です。
- カリカリ
- むにゅっ
- ふわふわ
- ばりばり
などのオノマトペは、海外からいらした方にとってもイメージしやすいと好評です。
日本人の感性の豊かさを表す大和言葉
雲にまつわる大和言葉
徒雲
浮雲
雲の梯
棚雲
鰯雲
入道雲
耶麻蔓
木綿蔓
からだに関する大和言葉
腰が据わる
腰砕け
腰がない
腰抜け
へっぴり腰
腹が決まる
腹をくくる
腹がない
腹を割って話す
日本人は、体や心の動きに対して敏感です。昔は着物や袴という、腰や腹を意識せざるを得ない衣類を纏っていたため、感覚が研ぎ澄まされ多くの表現が生まれたのだと思われます。
「ことば」とは?

「ことば」の語源は、奈良時代以降の「言の葉」に由来します。奈良時代といえば平城京という都が誕生して国家として整った時代。文化教育の整備も進んだことでしょう。それ以前は「こと」と呼ばれていました。
つまり、事柄や事象の「事(こと)」、口から発するのも「言(こと)」であり、言葉と出来事は「こと」という同じ言葉で表されていました。
なぜなら、日本古来の言霊信仰により、口に出した言葉や心に思った言葉は、本当の事として実現してしまうと考えられていたからです。
そういえば、世界中を恐怖に陥れてすっかり化けの皮の剥がれた感のある令和の感染症。あれも誰かの言霊だったのかも……。
どこまでもポジティブな大和言葉たち|本来の意味を紐解く
「ありがとう」は漢字で「有難う」と書かれることも多いため、その意味については概ねご存知でしょう。ここでは、以下のような日常的に使われている大和言葉の本来の意味を紐解いていきます。
- 春夏秋冬
- おめでとう
- たのしい
- てあて
春夏秋冬
四季の巡りに佇むとき、この日本に生まれてよかったと心から思います。その春夏秋冬の語源にまつわる説をご紹介しましょう。
- 春:春はあらゆる生命の芽吹く季節です。芽が「はる(張る)」として、生命力が溢れ出す季節を表現しているといわれています。
- 夏:夏の語源は「暑(あつ)」が変化したのではないかといわれています。
- 秋:秋は収穫の季節。「飽き(あき)」るほど食物があることに由来するとの説です。
- 冬:冬は春に備えて力を蓄える季節です。古代は物を振ることで霊力が増えると考えたため、「振る→増える」が語源といわれています。
おめでとう
「おめでとう」は「芽出た」状態を表すといわれています。芽が出るということは、それだけ成長したということです。
新年を迎えて一つ年を重ねた、ステップをひとつ駆け上がった、などの状態を示す言葉としてもちいられていたものがお祝いの言葉になったと考えられます。加えて、出た芽をしっかり育てなさいよ、という励ましも込められているようです。
たのしい
「たのしい」の「た」は「手」の音が変化したもので、「手の上にたくさん物が乗っている状態」を示しているといわれています。「たのし」とは「満腹で満ち足りた気持ち」であり、つまりお腹いっぱいになることこそが楽しいことだったのです。
現代人の感覚としては、「楽しい」はレジャーや買物などの経済効果によってもたらされたり、非日常的な刺激の多い状態だったりします。
しかし、生きていく根本に立ち返ったとき、やはりお腹いっぱい食べられることは有難く、そして楽しいことです。
てあて
子どもの頃、ケガをしたりお腹が痛かったりしたとき、母親がじっと手を当ててくれたことはなかったでしょうか? 柔らかくほんのり温かい母親の手に触れられると気持ちが安心して、痛みも落ち着いたような気がします。この母親の行為こそが「手当て」です。
手の平は「掌」とも書き、「掌(たなごころ)」とも読みます。「たなごころ」は「手の心」を意味し、掌から伝わる温もりには、心が感じる痛みを癒す力があるといわれています。また「看護」の「看」の文字は「手」と「目」でできています。つまり、手を当てて掌(たなごころ)で相手を看るということです。
【まとめ】心を込めた大和言葉で明るい未来を!
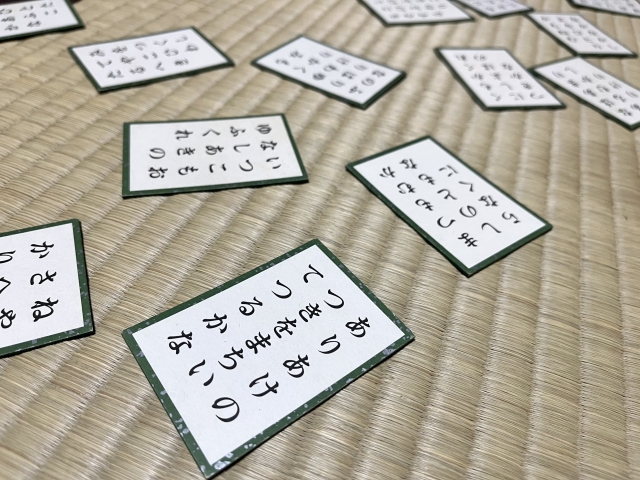
「大和言葉」は長い時を超えて今も私たちの生活の中に溶け込んでいます。声に出して安心できるのは、その霊力を持った響に心が呼応するからでしょう。
言葉が持つ意味を知ることで、いっそう心を込めて口に出すことができます。
膨大な情報に振り回され、ニュースのファクトチェックですらファクトのような時代になりました。こうした時代にこそ、言葉を大切にしてきた日本人の感性が活かされるのではないでしょうか。素朴でポジティブな「大和言葉」によって、世界の真の調和が実現する日はそう遠くありません。
参考文献:声に出して使いたい大和言葉/齋藤孝 扶桑社
やまとことば50音辞典/髙村史司 飛鳥新社
参考サイト:大和言葉 – Wikipedia



