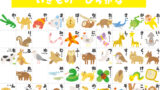为什么日语中有汉字、片假名和平假名?什么是片神名?什么是吴志文字?
The Japanese language uses three types of characters: hiragana, katakana, and kanji. How did this unique writing system come into existence? Furthermore, why have Yamato kotoba (traditional Japanese words) and ancient scripts such as Katakamuna and Woshite characters been gaining attention in recent years?
Here, we will explain the reasons why Japanese has hiragana, katakana, and kanji, as well as delve into Yamato kotoba, Katakamuna, and Woshite characters.
日语中使用三种文字:平假名、片假名和汉字。这种独特的文字体系是如何诞生的呢?此外,为何大和词(传统日语词汇)以及被称为神代文字的“卡塔卡姆那文字”和“和之手文字”近年来备受关注呢?
在这里,我们将解说日语中存在平假名、片假名和汉字的原因,并探讨大和词、“卡塔卡姆那文字”和“和之手文字”的背景。
日本語には、平仮名、カタカナ、漢字という3種類の文字が使われています。この独特な文字体系は、どのようにして生まれたのでしょうか?また、大和言葉や神代文字といわれるカタカムナやヲシテ文字が近年、脚光を浴びているのは何故なのしょう。
ここでは、日本語に平仮名・カタカナ・漢字がある理由と大和言葉、カタカムナとヲシテ文字について解説します。
なぜ日本では漢字・ひらがな・カタカナの3種類が共存しているのか?
日本語は漢字・ひらがな・カタカナの3種類の文字を持ち、それぞれの異なる役割が共存することで深い意味を分かりやすく伝えられるよう進化してきました。具体的には以下のような役割で分類されます。
- 漢字: 堅実なイメージ。意味を明確に伝えるために使用
- ひらがな:柔らかく親しみやすいイメージ。 文法的な役割(助詞や動詞の活用)を担う
- カタカナ: リズミカルで軽快なイメージ。外来語や擬音語、強調表現などに使用。
一般的には、文章を書く際、これら3種の割合が、
- 漢字:20~30%
- ひらがな:70%前後
- カタカナ:0~10%
の比率がもっとも読みやすい黄金比といわれています。
しかし、実際にはこれらの他にローマ字やアラビア数字、ギリシア文字などが混在した文章を見かけることも少なくありません。多言語を受け入れる寛容さとアレンジする柔軟さは日本ならではの特性といえます。
日本語の文字体系の成り立ち
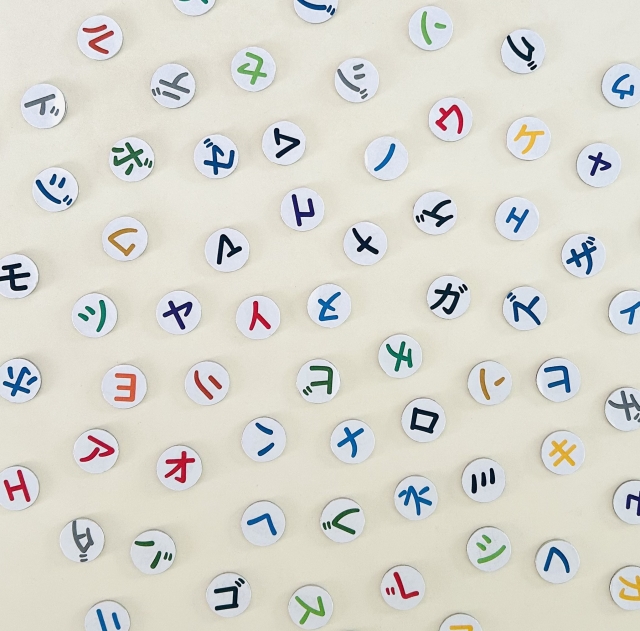
日本語として、漢字・ひらがな・カタカナが共存してきた背景には、他国との交流や実用性の融合があったと推測されます。
3種類の文字の共存は日本の歴史的な発展に由来し、それぞれの文字体系が異なる目的や役割を果たすために自然と共存するようになりました。
日本語文献を古い順に並べると、古事記〔712年〕・日本書紀〔720年〕・万葉集〔7世紀前半~759年〕となります。いずれも歴史教科書に記されている飛鳥時代(592~710年)、奈良時代(710~794年)にかけて、いわゆる天皇を中心とした国家としての形が整ってきた時代に編纂されたものです。しかし、それ以前の書物も各地に存在していたという説は、もはや多くの日本人が知るところとなっています。
ここではひとまず、教科書通りに漢字の導入からひらがな・カタカナ誕生の経緯を追ってみます。
1.漢字の導入(古い出土品は多いが、普及したのは5~7世紀)
漢字は4~7世紀の鉄器時代に中国や朝鮮との交流を通じて日本に伝わりました。『日本書紀』(720年)では、応神天皇時代に百済から渡来した王仁(わに)が『論語』と『千字文(せんじもん)』を用いて漢字を伝えたと記されています。ただし、『千字文』の成立時期(6世紀頃)と王仁の来日時期(4~5世紀)に矛盾があり、教科書の定説が見直されつつあります。
ちなみに、日本で発見された最古の漢字は約2000年前の吉野ヶ里遺跡の銅鏡に刻まれた「久不相見、長毋相忘」の8文字です。
やがて6~7世紀には儒教や仏教など大陸からの思想が浸透し、漢文書の読解力が必要とされたため識字層が拡大していきます。
2.カタカナの誕生(平安時代初期~の万葉仮名がベース)
漢字は画数が多く狭いスペースに書くのが困難で、しかも書ける人が限られていました。そのため、日本語としての音(響き)を表記するために、漢字の音だけを用いた文字である万葉仮名が生まれました。この万葉仮名を基として、カタカナとひらがなが作られていきます。
カタカナは、僧侶が漢文を学ぶときのフリガナやメモ書きのために用いたのが始まりといわれ、平安時代(794年〜1185年)初期から徐々に広まりました。たとえば「耶麻」という漢字に、書きやすい漢字である「也=や」と「万=ま」を添えて誰もが読めるようにしたといわれています。
その後、外来語や強調したい言葉の表記、あるいは擬音や擬態語などのオノマトペにおいて頻繁に使用されるようになりました。
ちなみに「カタカナ」の「カタ」とは、不完全を意味します。つまり、「ア=阿」「イ=伊」「ウ=宇」のように漢字の一部を使って作られたため「不完全な仮名」としてカタカナと呼ばれるようになったということです。
3.ひらがなの誕生(平安時代初期~女性に人気)
ひらがなは万葉仮名の草書体をさらに簡略化して作られました。主に女性や一般民衆が使用し、平安時代初期には女性が日常的な文章や文学に用いる「仮名文字」としてまたたく間に広まります。
空海が「いろは歌」やいろは手本を作ったという俗説もありますが、現実問題として、漢字だけでは日本の言葉、日本人の心持ちを十分に表現できないという思いがあったのではないでしょうか?
もっとも後発の文字ですが、流麗なフォルムはもっとも日本らしいといえるでしょう。
ひらがなは私的な場面や女性が使う文字として認識され、『土佐日記』では男性の紀貫之が女性を装ってひらがなで書いています。また、ひらがなの誕生により、手紙や和歌・物語・随筆などでの使用が増え、女流文学が花開く契機となりました。清少納言の『枕草子』や紫式部の『源氏物語』がその好例です。
大和言葉(やまとことば)とは?

大和言葉(やまとことば)は、日本古来の言葉で、漢語や外来語が入る前から存在していた固有語です。和語(わご)とも呼ばれ、和歌や雅語、女房言葉を指すこともあります。また、奈良県の方言を指すこともあります。
大和言葉は、日本の歴史の中で縄文時代から続く原日本語を強く残しています。縄文時代から弥生時代にかけて、朝鮮半島や大陸からの「弥生系渡来人」が移住し、在来の「縄文人」と混ざり合って現在の日本民族が形成されました。このような歴史的背景を経ても、縄文時代から使われてきた言葉が今も残っていることが、大和言葉の重要性を示しています。
カタカムナとヲシテ文字
「これこそが日本古来の大和言葉であり、日本人のルーツではないか?」と、近年脚光を浴びているのが、カタカムナ文字とヲシテ文字です。
神代文字とも呼ばれ、一つひとつの文字にエネルギーが宿るといわれています。
しかし、「日本には古来の文字がなかったから、数百年かけて漢字を輸入し仮名を創作してきたのだ」と述べる学者も少なくありません。けれども、輸入された漢字を訓読みし、カタカナとひらがなを駆使しているのは、本来の日本語があった何よりの証拠ではないでしょうか?
ここでは、カタカムナ文字とヲシテ文字を紹介します。
カタカムナとは?
カタカムナ文字は、円と直線の組み合わせからなる幾何学的図形の文字です。そのカタカムナ文字によって、中央から渦巻き状に綴られたものをカタカムナ文献と呼びます。この文献は「カタカムナ神社」のご神体であり、古代日本の科学技術や哲学を記した書物とされています。
縄文時代以前から使われ、日本人のルーツを探る手掛かりの一つとされる一方、発見が1949年と新しいため、公的な学会からは学術的に認められていません。
カタカムナウタヒ80首の中には、日本語の48音が重複なく記載され、すでに日本語の音が存在していたことが推察されます。「カタ」は「見えるモノ」で不完全、「カム」は「見えないモノ」で神を指し、「ナ」はそれらを統合した核、すなわち本質を意味します。
すべての存在は「カタ」と「カム」が繋がり、「ナ(名)」という核で一つに溶け合う根元を持っています。外は内によって創られ、宇宙にはそれしか存在しないとされます。この理解から、思いを現象化、物質化するのが「カタカムナ」です。
ヲシテ文字とは?
ヲシテ文字は、縄文時代の日本で使われていたとされる神代文字で、「教える(をしへる)」の「をし」と手段を表す「て」が合わさった言葉です。基本的に48文字から成り立ち、現在の五十音に対応しています。日本の歴史書「ホツマツタヱ」や「ミカサフミ」にも使用され、神事や占いに使われる表意文字です。
ヲシテ文字を伝える文献として「ホツマツタヱ」「ミカサフミ」「フトマニ」の3つがあり、これらを総称して「ヲシテ文献」と呼びます。文字は記号のように見え、一文字一文字が神様を表しています。
「ヲシテ文字」という呼称は、文中でこの文字が「ヲシテ」と表記されているからです。江戸時代中期には発見されていたといわれていますが、その真贋については議論が続いています。もし本当に存在していたなら、古代日本には漢字伝来以前の高度な文明が存在していたことになります。
文字・言葉でこれだけワクワクさせてくれる日本の良さを再認識!

日本のひらがな・カタカナ・漢字のように、役割や用途が明確に分けられている3種類の文字を併用する仕組みは非常にユニークです。しかも、文字そのものにエネルギーが宿るという神代文字の存在。言葉が心の現れであり、言葉を大切にする国民性が見てとれます。
その多様な文字体系が豊かな表現力を可能にし、詩的に、かつ文化的にも深くしています。わずか三十一文字で物語を奏でる和歌や十七文字の俳句が、世界に稀な文化芸術として根付いたのは必然でしょう。日本人の豊かな感性があってこその日本語が、今後も美しく奏でられ、よりよい世界づくりの一助となることは間違いありません。